このブログでは麻雀のアプリをやる上で必要なルールを示してきます。アプリではなくリアルの麻雀に必要なルールについては、アプリで最低限のルールを知ってもらってからの方が理解しやすいと考えているため、まずはアプリをやる上でのルールを優先します。
・1局の流れ
最初に4人各々に13牌ずつ配られ、順番に1牌引いて(ツモ)不要となる1牌を捨てる。これを繰り返していき和了りを目指していく。途中で誰かが和了った場合、もしくは最後まで和了りが出ない場合(流局)に1局が終了となる。
・和了りの形
麻雀における基本の和了りの形は順子(シュンツ:数字の順番の組み合わせ3つ)または刻子(コーツ:同じ牌の組み合わせ3つ)を4組+雀頭(ジャントウ:同じ牌の組み合わせ2つ)を1組の合計14枚の形となります。例えば以下のような形を作ることができれば、和了りの形が成立します。以下の例では「三四五」及び「⑤⑥⑦」がシュンツ、「一一一」及び「白白白」がコーツ、「88」がジャントウで、シュンツまたはコーツ、の組み合わせが計4組とジャントウが1組で合計14枚の形として成立しています。
一一一三四五⑤⑥⑦88白白白
※漢数字が萬子(ワンズ)、〇囲み数字が筒子(ピンズ)、数字が索子(ソウズ)を表現しています。
普段は手牌は13枚で進行し、牌を引いてきて14枚となります。なので14枚の和了りの形になるひとつ前の状態が存在し、それを聴牌(テンパイ)と呼びます。この状態から和了りに必要な牌を引いてくれば下記の通り和了りの形となります。自分で引いてきて和了りの形が成立した場合、ツモ和了りと呼びます。
一一一四五⑤⑥⑦88白白白 ←テンパイ(三または六を引いてきたら和了りの形成立)
↓
一一一四五⑤⑥⑦88白白白 三 ←和了りの形(三を引いてきたので和了りの形成立)
↑(ツモ牌:引いてきた牌)
上記は自分で引いてきたことで和了りの形が成立した例を示しましたが、自分以外の誰かが和了りに必要な牌を捨てた場合、こちらも和了りの形が成立します。相手が捨てた牌で和了りの形が成立した場合、ロン和了りと呼びます。
なお聴牌の前の状態も用語があり、聴牌の一つ前の状態を一向聴(イーシャンテン)、2つ前の状態を二向聴(リャンシャンテン)、3つ前の状態を三向聴(サンシャンテン)とそれぞれ呼びます。
なお後に紹介するゲームのチュートリアルや動画解説などでもシュンツやコーツ、和了りの形を丁寧に解説してくれているので、そこで覚えることも十分可能です。
・和了りの条件
和了りの条件は和了りの形に加えて”役”を成立させる必要があります。
麻雀には30以上の”役”が存在し、これが麻雀を難しくしている要素の一つです。ただし、出現頻度が高い役は限られているため、まずは出現頻度が高い役を覚えていき、徐々に出現頻度が低い役も覚えていければよいと思います。
・半荘戦の流れ
対局が始まる際に始めに親を決めます。親となった人から最初にツモをして開始します。親が和了り1局が終われば引き続きその人が親となり(連荘)、親が和了らず1局が終了となれば次の人が親となります。そして全員が親を2回ずつ行っていき、最後の親の人の番で1局が終われば半荘戦が終わります。
・東風戦の流れ
半荘戦と比較して全員が親を1回ずつ行っていき、最後の親の人の番で1局が終われば東風戦が終わります。
・勝敗の決定
対局前に全員に25,000点の点数が付与されます。対局を進めていく中で、和了りが発生することで点数が増減します。そして対局が終了した時点で点数を多く持っている順に順位が決定します。

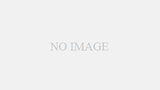
コメント